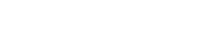1945年 アマガサキの戦後
終戦により軍需工場が閉鎖され、多くの労働者が失業するとともに、住宅難や食料難、インフレなどで市民は戦前のおよそ半分にまで減少。学校や病院、工場などは戦災で焼け、街には復員軍人や引揚者があふれた。栄養失調や病気による死亡者も多く、まるで皮をむくようにしてやっと生活していたことから終戦後の人々の暮らしは「タケノコ生活」などと呼ばれた。
復興の尼崎市政

八木林作(やぎりんさく)
官選最後の尼崎市長。在任期間は1943~1946年。鳥取県知事、神戸市助役などを歴任し、兵庫県知事から市長推薦を受けて尼崎へ。戦中~戦後の混乱期の市長として尽力。
焼け野原の尼崎を、9月18日にはさらに追い打ちをかけるように水害が襲った。戦後初の議会はまさに混乱極める9月26日に開かれている。
1946年3月の議会では、戦後処理に関する施政方針演説が八木林作市長によっておこなわれた。戦争関係経費の廃止など敗戦による制度の改廃や、食料の増産確保など市民の暮らしの安定策、について説明。しかし、急激なインフレと水害などの復旧が「本市復興ノ癌」だと苦悩を語っている。
しかしGHQの指令による公職追放で、八木市長や数名の市議会議員、ほぼすべての連合町会長などが職を退くことに。1947年4月には初の公選市長選挙で六島誠之助が当選し、復興のバトンが引き継がれている。
伝説の闇市
戦時中から主食をはじめとした生活必需品は配給制度のもとにあったが、こうした配給ルート以外に物資を手に入れる、いわゆるヤミ行為が公然とおこなわれていた。戦後には、さらに大っぴらになり、1945年10月頃にはりっぱな市場になっていたという。
市内7カ所にあった大きなヤミ市場の中でも、三和市場の西の裏通りや玄番掘と呼ばれた用水路に板をのせて商売をした「新三和市場」が最大の規模を誇った。元工員や引揚者、外国人など雑多な顔ぶれが軒を連ねたため、争いが絶えず警察以外に、これらを抑える存在が必要だったという。ここでは高木組がその役割を担い、1946年の終わりにはバラックを100戸建設し分譲し「三和復興市場」と名付けて発足。これに触発され、戦前からあった三和市場も店を開きはじめ「阪神間の台所」へと発展していくのだった。
「三和復興市場」は1949年から「新三和市場」と改称。現在の新三和サンロード商店街の前身である。阪神間にさきがけて巨大ヤミ市が発達した背景について、三和復興市場会長をつとめた池田清一氏は、周辺に比べて取り締まりがゆるやかだったと指摘している。
行政の復興が水害とインフレによる予算不足で停滞する一方、尼崎では商店街や市場を舞台に躍動感あふれる復興がはじまっていたのだった。
産業の復興
軍需生産が打ち切られた市内の工場は、従業員の整理、いわゆるリストラをはじめ、これに対して戦前から労働運動がさかんだった尼崎市では、その指導者らが中心になって労働組合が早々と結成された。1945年12月には「尼崎工業会(尼崎経営者協会の前身)」が結成。70社が加盟し、労働争議に対して工場の経営者たちも団結を見せている。
その後、尼崎の産業は鉄鋼業を中心に政府の保護を受けながら急速に回復。1950年に起こった朝鮮戦争で、再び「鉄のまち」としてよみがえっていったのだった。
1945年9月、戦後初の議会では、戦後経営のための委員会が設置され、市議会議員と市内の有識者あわせて25名で復興や水害対策ともう一つ、園田村合併問題が話し合われていた。
すでに昭和17年に武庫村、大庄村、立花村を合併して市域を広げていた尼崎市は、園田村にも合併を申し入れていたが拒否されていた。その理由は、伊丹市や川西市、宝塚市もいれて「大尼崎市」にするべきだというもの。
戦後になり復興事業をすすめるにあたり、1946年に再度尼崎市から合併を申し入れた直後、伊丹市からもプロポーズが…。一緒になるのは尼崎か、伊丹か?役場のボイコットや暴力事件が起こるほど壮絶な綱引き合戦の末、1947年3月に尼崎市と合併。今の尼崎を形作った戦後復興の大切な一コマなのである。
『尼崎市史第十二巻』『尼崎の戦後史』

『尼崎市史第十二巻』は第1章「戦後処理」からはじまる戦後の尼崎市を知ることのできる一冊。「昭和20年尼崎市事務報告書」は混乱の時代に膨大な業務をこなす市役所の姿が記録されており、感動すら覚える。『尼崎の戦後史』では読み物として戦後の尼崎の情景をたどることができる。
市内図書館、地域研究史料館などで閲覧可能。

1946年8月には、国の戦災復興院が尼崎都市計画区域の変更を認可。戦災復興土地区画整理の対象となったのは、国道2号と阪神電鉄沿線の区域で、1958年まで市街地整備が続いた。建物疎開で撤去された本町通り跡に、浜手幹線(国道43号)を建設したのもこの事業の目的だった。
完成した阪神尼崎駅南側の駅前広場(『尼崎戦災復興誌』昭和35年より)