ガイジンさんと呼ばないで 私が尼崎で暮らす理由
54カ国12,780人。尼崎市内にはこれだけの数の外国籍市民が暮らしている。もともとこの街で生まれ育った人も多いが、はるばる海を渡って来た人たちもしっかりと根を下ろし始めている。きっかけは仕事や夢、恋愛や結婚…とさまざま。尼崎を「多文化」に彩る人たちに話を聞いてみた。
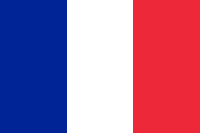 ブランド名になったフランスパン職人
ブランド名になったフランスパン職人

尼崎に住むフランス人を何人か紹介してくれた。インターネットや街を歩き、関西に住むフランス人とのつながりを大切にしているという。
「どうも、ルビアン・ミッシェルと申します」。ぺこりとおじぎをして名刺を差し出すパン職人。流暢な関西弁を話すミッシェルさん(51)は今年で来日31年になる。
フランス・ブルターニュ地方にある老舗パン屋の4代目。専門学校を卒業後、兵役でタヒチに滞在したのをきっかけに「もっといろんな国が見たい」と海外への関心が高まった。専門学校時代の先輩が働いていた縁で菓子店エーデルワイスに就職。たまたま出会った街が尼崎だった。
日本のことはほとんど何も知らなかった当時20歳のミッシェル青年。「昼間はフランスパンを焼いて夜は柔道を習っていました」。食文化や言葉の壁なんて感じなかったと振り返る。

「やっぱりミッシェルが焼くフランスパンへの評判はよかった」というのは本社営業部長の山本憲司さん。本場のパン職人が焼くお店をと、彼のファミリーネーム「ルビアン」を冠したブランドが82年に立ち上がった。フランスの老舗4代目は尼崎で家業を続けることになった。
現在では大阪を中心に4店舗、製造スタッフ34人を抱えるお店の指揮を取る。鮮度と焼き加減にこだわる「明太子フランス」で和洋折衷の味を作り出す一方、故郷に伝わるパン「クィニーアマン」の伝統の味も守り続けている。
 世界を知り、たどり着いた街
世界を知り、たどり着いた街

日本で暮らして不便なことは?「んー、特にないなあ。でも、夏の暑さだけは苦手だね」
セネガル政府の漁業省職員だったジョン・ベルナール・マサさん(41)は、国際協力機構(JICA)の研修で来日。タンザニア、インドネシアを訪問した後だった。「技術力はもちろん、仕事に打ち込む日本人の姿に感激した」。97年、研修で出会った日本人と結婚。彼女の実家がある尼崎へ移住し、二人の子どもに恵まれた。
日本語は、新聞配達をしながら語学学校に通って習得した。当初は公用語であるフランス語を活かした仕事を探したが、日本では「フランス人が優遇される傾向が強い」ため断念。久々知の部品加工メーカーで、エンジニアとして働いている。 一方で、毎月阪神尼崎駅前でホームレスのための炊き出しを手伝う。何度か会ううちに親しくなった人も多く、リストラやアルコールなど個々の事情にも耳を傾ける。少年時代はボーイスカウトの隊員として過ごした。「話を聞くだけでも、自分にできることをしたい」。ボーイスカウトが説く奉仕と融和の精神が、今の基礎になっているという。
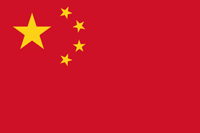 「食」で万里を越える
「食」で万里を越える

2002年に、NPO法人関西障害者国際交流協会を設立。田山さんは理事長を務める。
中国の肉まん、ベトナム生春巻き、韓国チヂミなどを集め「アジア家庭料理試食会」を昨年はじめて開いた。「国際交流は難しいことじゃない。食をきっかけに互いの文化にふれあうことができた」と話す主催者の田山華栄さん(48)は北京で生まれ育ったチャイニーズ。生まれながら脊髄に障害を持つ彼女だが、中国では公務員として障害者の自立支援に積極的にかかわった。
支援活動で出会った日本人男性からの熱烈なプロポーズを受け、15年前に尼崎へ。「不安だったけど、私たちの結婚が最高の日中友好だと思って」と照れながら当時を振り返る。
来日後も、料理教室、中国人画家の個展など精力的な活動で、尼崎に住む韓国人やベトナム人とのネットワークもできてきた。
「もっと色んな国の人と交流していきたい」と意気込む田山さんらは、今秋「家庭薬膳講習会」を計画中だ。障害者と外国人、いわゆるマイノリティの壁を「食」でぶち破る彼女が頼もしい。

